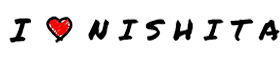西田町の土棚に関下というところがあり、そこには関所(せきしょ)跡がある。
関所というのは、国境などの道に、そこを通る人や、運ばれる物を調べるために作られる門と建物のことを言う。
昔、いつのころかわからないが、土棚のその辺りが国境であったために関所が作られたのだという。
しかし、やがてその関所は廃止されて「関下」という地名だけが残された。
それからまた時は過ぎて、寛文七年(1668)に、田畑の面積や米の収穫量を調べる検地(けんち)が行われた。
その時、関下の検地をおこなった藩史(藩の役人)は、
「なぜここの地名には『関』の字があるのか。関所でもないのに、『関』を使ってはならない。土地名をかえるように」
と命令した。
しかし、村人たちは、
「ここは昔の関跡であるから、どうしてもそのことを地名として残したい」
と申し出て、特別に藩の許しをもらったと伝えられている。
〇「高野郷土史」(再話 渡辺雅子)
参考文献『郡山の伝説』
昭和61年3月10日発行
監修 東洋大学教授・文学博士 大島建彦
発行 郡山市教育委員会
編集 郡山市教育委員会社会教育課
―コメント― I ❤ NISHITA
ところで、「関下の関所跡」どこにあるか知ってますか?
知ってる人、ぜひI♡NISHIAに教えてください!