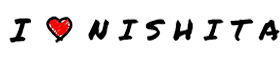日枝神社(三町目)

説明
日枝神社(ひえじんじゃ)は平安時代の延暦19年(800)に創建された神社。
ご祭神は大己貴命(おおなむちのみこと) 大山咋命(おおやまくいのみこと)
社殿は山王山の頂近くに建てられており、本殿部分が岩の洞窟の中に鎮座しているたいへん珍しい神社である。
同名の神社が同町内の根木屋にも鎮座している。
メモ
神社は半分岩の中にうめこまれたように建てられており、すぐ前にも巨石がせまっています。
春には神社裏にそびえたつ樹齢500年の山王桜がみごとです。
所在
郡山市西田町三町目山王169

もっとくわしく
奈良時代の延暦10年(791)征夷大将軍坂上田村麻呂が東征の時、京都北面の武士・藤原氏若狭太郎が、守護神日吉大権現を負いて従軍し、東奥を平定しました。
のちに田村麻呂は帰朝(798)しましたが、若狭太郎は当地に土着して、延暦19年に山王山に神霊地を撰しまして守護神を安置し、岩神社山王大権現と崇め神官となりました。
若狭太郎の寂後、子孫藤原朝臣猿子隼人介成正が神主となりました。
また、明治2年から日枝神社と称しました。
社殿は、山王山の頂近くで、海抜312.8mの地にあり、本殿は岩の洞窟の中に鎮座しており、極めて稀であり貴重な存在であります。
日枝神社由緒より